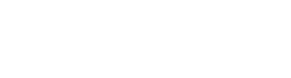最近はあまり見なくなりましたが、信号待ち中にヘッドライトを消灯する車について。
交差点の赤信号で停止中にヘッドライトを消すか消さないか、その行為が違反か違反ではないかは定期的に話題となります。
ヘッドライトを消灯する行為は眩しくないように配慮しているものですが、これを推奨する声や、また消灯は違反だから消すなと言った声。
先に結論をいうと信号待ちでのヘッドライト消灯は道路交通法違反ではありません。では、記事内で条文を元に見ていきましょう。
道路交通法第52条
道路交通法では以下のように定められています。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
出典:道路交通法第52条第1項 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの
車両は夜間、道路にあるときはヘッドライト(前照灯)を点灯させなければいけません。
これだけ見れば信号待ち中も点灯しないと違反という感じになりますが・・・
道路交通法施行令第18条

ところが道路交通法施行令の第18条を見ると次のようになっています。
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
出典:道路交通法施行令第18条第1項 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの
道路交通法第18条第1項には夜間道路を通行するときに自動車は前照灯(ヘッドライト)の義務。
で、信号待ちに当たる停車(法令の規定による停車となる)については道路交通法施行令第18条第2項。
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
出典:道路交通法施行令第18条第2項 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、夜間駐停車する時は非常点滅表示灯か尾灯か駐車灯を点けなければならない。
※ただし
- 道路照明などで50m後方から見える場所に駐停車しているとき。
- 夜間用停止表示器材や警告反射板をおいて駐停車しているとき。
はこの必要はない。
つまり信号待ち中は ヘッドライトを消していても 尾灯(テールランプ)が点いていれば 違反ではない。
道路交通法第52条第2項(行き違う場合)
道路交通法第52条第2項もよく話題に上がるので。
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
出典:道路交通法第52条2項 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの
行き違うとき、ここに「灯火を消す」とある部分で、ヘッドライトを消していいと勘違いしている人がいます。
しかしこれは大きな勘違い。
道路交通法第52条2項の「政令で定めるところ」とは、道路交通法施行令第20条(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)のこと。
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
出典:道路交通法施行令第20条(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)※赤色マーカーは当サイトで引いたもの
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
すれ違い用前照灯とはロービームのことです。
走行用前照灯とはハイビームのことです。
前部霧灯とはフォグランプのことです。
※車幅灯はスモールランプ(ポジションランプ)のこと。
※1万カンデラですが、車の場合はヘッドライトは一般的に1万カンデラを超えています。
つまり道路交通法施行令第20条の他の車両等と行き違う場合の「灯火を消す」というのは走行用前照灯(ハイビーム)を消灯することであり、「ロービームも含めたヘッドライトを消す」という意味ではありません。
信号待ちのヘッドライト消灯は危険である
信号待ちのヘッドライト消灯が危険である理由を書きます。
存在が見えにくい
私が通っていた教習所の教官から授業で聞いた話ですが、道路が狭く小さな見通しの悪い交差点での信号待ちで、ヘッドライトを消灯していた先頭車両が、左折車から追突された事故というのがありました。
交差点の道路脇は建物と塀で見通しが悪かったということらしい。

つまり左折時に先頭がヘッドライトを消灯して暗かったので存在を見落として追突したらしいです。ヘッドライトを点灯していれば存在を大きくアピールできていたのでこの事故は起きなかった可能性があります。
消したまま発進するリスク
信号待ちにヘッドライトを消すと、発進時に点灯させなければいけません。
日常的に何百回とやっているとそのうち1回くらい点け忘れる可能性があります。その1回が事故になることがあります。ヘッドライトを忘れると交差点で直進中に右折車が突っ込んできますので大変危険です。
信号待ち停止中はロービームで待つべし
信号待ちでヘッドライトを点灯することは蒸発現象が起きて危険だという主張もありますが、実際交差点で多くの車がヘッドライトを点灯していますが、ハイビーム停車ならともかく、殆どの車がロービーム停車であり、実際運転しても蒸発現象など感じたことはないです。
昔は信号待ちで周りが眩しくないようにと、善意でヘッドライトを消してスモールなどにしている車も多かったようですが、最近はヘッドライトを消す車は全くと言っていいほど見なくなりました。それで全く問題なし。信号待ちはロービームでOKです。
ただ交差点の停止線手前が傾斜してい光軸が上向きとなる場合、交差点向こう側で信号待ちしているドライバーには相当眩しいので(特に最近のLEDは)、そういう時はスモールにしてもいいかもしれません。
ただし、青に変わって発進するときにはヘッドライトを点け忘れないように特に注意しないと、その時点で違反となります。