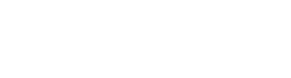制限速度30km/hや40km/hの道路で、車の流れが50km/hや60km/hなんてことはよくある光景。まれにきちんと制限速度を守って走るドライバーもいるが、そういう法遵守ドライバーに対し、ネット上での声は冷ややか。
「流れを阻害している」「遅すぎるのも迷惑」「独りよがりな走行は危険増大」などと否定。
一方で、高速道路の追い越し車線、高速道路の工事規制区間、一般道でのバイパス、生活道路などで制限速度(法定速度や指定速度)を大幅に超える流れが常態化し、交通事故が耐えないことが問題化。
この記事では、「法より流れが大事」というドライバー独自ルールを正当化しようとする風潮が強い問題点を指摘します。
狭い山道や通学路に多い30キロ40キロ制限道路
この山沿いの道は道路幅も狭く曲がりくねり、また歩道も路側帯も狭い。歩行者や自転車は少ないが、ここは自動車専用道ではなく、狭い道路を普通自動車や大型トラックなどがビュンビュン飛ばされると歩行者や自転車にとってはとても危険。狭い上に中央分離帯もなく、万が一対向車がはみ出してぶつかったときも速度が低いほうが被害は少ない。
30キロ道路を抜け道として自動車が制限速度を大幅に超えて流れているようなところは多く、歩行者とのニアミスや事故が多発していて問題化。そのため移動式オービスやペースメーカー車導入という運動が活発になってきています。
居住行動圏内の道路なども、普通自動車や大型トラックが60km/hでビュンビュン流れていると危険。路側帯も狭く家の玄関のガラスを拭き掃除することさえ出来ません。建物の影からすっと人が出てくることもあるかもしれません。何かあったときに対応できるように最高速度を法定速度よりも低く指定してあるのは当然で、これが守られないと安全に生活できません。
その他、こういった場所でも40km/h制限がありますがこの国道43号線には理由があります。よく見ると速度標識の下に「環境対策」という補助標識が見えます。
1976年の国道43号線道路公害訴訟で、騒音・振動・排気ガス差し止めと損害賠償を求めた訴訟。この影響で、法定速度より低い最高速度を指定しているものです。なので規制標識を無視し、ここでドライバー独自ルールで勝手に60km/hや70km/hで流れを作ったりすると何の意味もないんです。
「なぜ最高速度を規制するのか?」について警察庁の考え方を以下のリンクから見ることが出来ます。
制限速度を超えるのが当たり前?
福岡県~佐賀県にある久留米基山筑紫野線は原付も走れる一般道であり、法定速度60km/hだが、流れが速すぎることが多く、道路上に「ここは高速道路ではない」という注意書きが設置されています。
また、下のストリートビューのような高速自動車道ではない自動車専用道(小郡道路、70km/h制限)でも、状況によっては100km/hほどで流れる事があり、その流れの中を更に速度を上げた車が追い越していく。
こういった道路で制限速度(法定速度や指定速度)をきちんと守って走る少数派のドライバーが、制限速度を超えて走る多くのドライバーから見れば邪魔な存在となっている実態。
なぜ制限速度より流れが早いのか
まず全体的な問題は、ほとんどのドライバーが速度標識を全く見ないことです。というか標識全般を殆ど見ないドライバーが多い、信号しか見てない。教習車に乗っていた頃は交通ルールをしっかり守っていて、免許が取れた途端、学んだことをすべて忘れ好き放題に走る人が多い。
一般道は法定60km/hなら問題がないと思っているドライバーも多い。30km/hや40km/h制限でも関係なく50-60km/hで流れている。さらに抜け道となっている場合は、もっと速い速度で駆け抜けていく車が多い。
もうひとつは取り締まり対象やメーター誤差があるから制限速度+10km/hまでは大丈夫といった理由で速度を上げ、流れが速くても罪悪感がなくなる。じゃあもう+5km/hでもいいか、のような心理も生まれやすい。
たとえ制限速度を超えて法を違反していても、「周囲が皆その速度で走っていれば大丈夫」というような、「ここは50km/h制限だが80km/hで流れているのでそれが正解」という感じで罪の意識は消え同調心理が支配する。
こうなってくると、制限速度で走ると速度差があって危険、という負の連鎖が起こり、どんどん朱に染まって速度違反車が増えていく。
流れ優先思考の決定的な盲点
制限速度(法定速度や指定速度)より流れが大事という理論は危険。日本人の怖いところは「皆がやっていれば違法でも正しい、多数派が正義」だというような空気が非常に強いことです。
「みんなルールを破っているんだからお前も破れ!じゃないとルールを破っているみんなに迷惑だ!空気読めよ!」という同調圧力。迷惑なのはルールを守らない自分たちであるということに気がついていない。
ルールを守らない多数派が、ルールを守っている少数派を異質扱して叩く構図。ただの集団迷惑行為である。
彼らは40キロ制限の道路を40キロで走る車に対して「チンタラ」「ノロノロ」という言葉を使うが、制限速度を超過し、40キロ道路でも60キロ70キロで走るのが日常になると、制限速度で走る車が「チンタラ」に感じてしまうようになる。自分視点から物事を見ているからである。
速度遵守より流れを肯定する言い分に、道路交通法第1条の「目的」を持ち出し、円滑を強調する人がいました。
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
出典:道路交通法第1条
ですが大事な言葉を見落としています。まず最初にあるのが、「道路における危険を防止し」ということです。それ以降はその他であり、主従関係は道路の危険防止>交通の安全と円滑、障害の防止。
- 道路の危険防止とは
「道路における交通事故等の危険を防止するため。」。 - 交通の安全と円滑とは
「道路を通行する者が、安心かつスムーズに移動できるような道路交通環境を確保するため。」。 - 道路の交通に起因する障害の防止とは
「車の走行に伴い発生する大気汚染、騒音及び振動により人の健康又は住民の生活環境に生ずる被害(交通公害)を防止するため。」。
出典:交通規制の目的|警察庁
日本の道路は60キロの場所でも40キロの場所でも関係なく60キロあるいは70キロ位で流れる傾向があるが、「円滑な交通」や「流れ」というものは、法を守った速度内での話であり、事故が多発したから40キロに規制されたような場所を、ルールを無視して60キロ70キロなどという速度超過した流れは、そもそも道路に危険性が及ぶので論外。
円滑というのはスピードを出して短い時間で移動することではなく、ドライバーに交通のルールを守らせることで歩行者や車の交通整理をし、あらゆる交通が留まることなくスムーズに流れるようにという意味。決して速い流れ=円滑というわけではないということ。
「安全で円滑」というのは特定の場所の駐停車を禁じたり、信号を守らせたり、進行方向別に車を整列させたり、歩行者を優先したり、こういうもの。追いつかれたら譲らないといけないという道路交通法第27条第2項を言う人もいますが、これは制限速度内の条件があり、速度違反した車が追いついても義務は生じません。
つまり、交通の円滑は法を守った速度内での話。速度違反はそもそもが論外。
流れに合わせることも大切というのは制限速度内での話。制限速度を越えた流れに合わせろというのはそもそもが論外。
危険を作っているのは自己ルールで制限速度を超え危険な流れを作っているドライバーたち。ルールを守ったドライバーに迷惑をかけているという自覚がなさすぎる。
ペースカー導入の試み
生活道路や高速道路の工事規制区間では実勢速度が制限速度を大幅に上回り、歩行者や工事関係者が危険な状態となっているため、各地でペースメーカーを導入する試みが増えています。
ペースメーカー車を入れることで危険な実勢速度を制限速度内に抑え込みます。
迷惑なのは速度を守っているドライバーではなく、制限速度を越えた流れを作り、ルールを守っているドライバーへ迷惑をかけている側。多数派が正義・ルールではありません。ルールを作るのはドライバーではない。
法で定められた最高速度より、ドライバーたちが勝手に作り上げた流れが大事なら(法を違反してもそっちが大事なら)、そもそも道路交通法も運転免許もいらない。道路交通法も免許も全く意味がない物になってしまう。
流れ優先の速度違反だの、制限速度より大きく飛ばしていれば高速の追い越し車線を走り続けてもいいだの、赤信号に変わっても加速して2秒は突っ込むだの、一時停止は徐行で通過だの、ウインカーは曲がる直前で点滅だの、駐停車は半分歩道に乗り上げて止めるだの・・・それは秩序がないただの無法地帯。
交通ルールをどうしても守りたくないならね、免許を返納して車を降りることをオススメします。じゃないとルールを守っている人に迷惑。